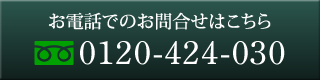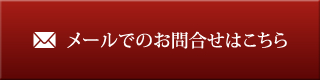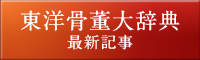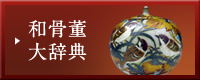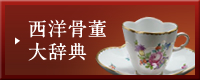汝官窯は河南省宝豊県にあった窯です。宮廷で使用される器の制作を行った『官窯』であったと同時に、大衆向けの作品も制作していました。
時代的には1086年~1106年頃の約20年間しか活動していなかったとされていますが、汝官窯で制作された『天青色』の青磁は、鑑賞家の間では非常に有名です。ここではそんな汝官窯について、ご紹介していきます。
汝官窯の青磁と歴史
汝官窯では当初、大衆用に印花を施した青磁を焼いていましたが、北宋時代の末頃にはその品質の高さから、宮廷に納める磁器のみを焼く専属の「官窯」として認定されました。その後、国が金に攻められ靖康の変で滅びるまでの約20年間、汝官窯は青磁の生産を続けます。
汝官窯で最も有名な『天青色』の色合いは独特なもので、緑色を帯びた青色が、淡い光沢を放っているように見えるのが特徴です。この絶妙な色合いは中国の皇帝の言葉が由来しており、陶工たちが皇帝より『雨上がりに雲の切れ間から除く空のような、そんな色の磁器を作るように』と命ぜられたのがきっかけだと言われています。
天青色を作り出す特殊な釉薬には現地で豊富に採取された瑪瑙が使われたとされており、焼成方法には支焼満釉という方法が使われました。これは「支焼具」といわれる釘などの道具で高台を支えて焼き上げる方法で、焼成後には高台の内側に支焼具で支えたごく小さな跡が付くかわりに、全体に釉薬をまんべんなく付けることができる焼成方法です。
現存する汝官窯の作品にも、小さめの物には3つ、中~大きい物には5つの支焼具の跡が見られるそうです。
ちなみに、日本国内では東京国立博物館や東洋陶磁美術館で目にすることができます。