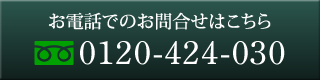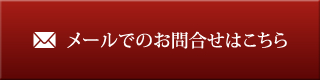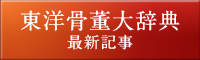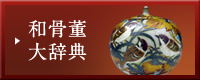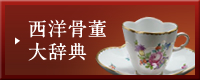三彩陶器はその名の通り、3色の釉薬を使って装飾された焼き物のことです。酸化鉛を呈色剤として緑色に発色する酸化銅や、褐色や黄色に発色する酸化鉄を加えて焼き上げることにより完成します。紀元前の前漢の時代に発達したと考えられており、当初は墓葬用の副葬品として流通していました。
やがて素地に化粧土を掛けた白釉陶器が出来上がると、これに鉛釉を使った装飾が行われ、三彩陶器の基礎が出来上がりました。その後時代ごとに三彩陶器は制作され、現在でもその美しさが称賛され、鑑賞を目的としたコレクターに人気の高い作品の1つでもあります。
ここでは時代ごとに、中国の三彩陶器をご紹介していきます。
☆唐三彩
7世紀の後半から8世紀前半に焼かれていました。中国ではほとんどが墓葬用の副葬品として使われており、王や貴族、高官などその身分に応じて副葬される数も制限されていたようです。
鮮やかな色使いと装飾で、三彩と言えばすぐに名の上がる唐三彩ですが、唐時代中期の安禄山の乱を境に一時衰退しました。しかし最盛期は当時奈良・平安時代であった日本にも輸出され、寺院や墓からも見つかっています。
☆渤海三彩と遼三彩
8世紀の前半、北方の民族によって建国された渤海国では「渤海三彩」が焼かれました。副葬品としてだけでなく建築用陶器も制作され、日本にも伝わっています。
また、10世紀の初頭には契丹族が建国した国、遼で、遊牧民族ならではの文化と唐三彩の文化が合わさった「遼三彩」が制作されました。こちらも副葬品とされていましたが、動植物をモチーフとした素朴な装飾をした皿や壺などの作品が見られます。
☆宋三彩と元三彩
唐時代の中期に衰退した唐三彩が復活し、宋三彩ではそれまでの副葬品ではなく、実用陶器が制作されました。中でも陶枕(とうちん)と呼ばれる陶製の枕は華やかな装飾をされたものが多く、山水や人物、動植物など様々な図柄の物が見られます。このような生活用品以外にも瓦などの建築用陶器も制作され、三彩陶器が副葬品から日用雑器として流通して行きました。
また、元の時代に作られた元三彩には、美しい青緑色に発色する翡翠釉、または孔雀釉と呼ばれる釉薬が使われ、それまで以上に鮮やかな発色の三彩陶器が制作されるようになっていきます。
☆明~清時代の三彩
明時代の三彩陶器に多く見られる装飾技法に、「法花」と呼ばれる技法があります。これは細い土紐を素地の上に貼り付ける「突線(堆線)」で描いた模様部分に褐色釉や緑釉を施す装飾方法です。この「法花」は特に景徳鎮窯でよく用いられ、細かな装飾と鮮やかな色合いを組み合わせた作品が多く生み出されました。
明時代の後期からは三彩の技術を用いた、香合などの比較的小ぶりなやきものが制作され、日本に輸出されると「交址焼き」と呼ばれ広まっていきました。
その後も三彩陶器は日本で人気を博し、京焼などでは中国三彩の写しなども見られます。