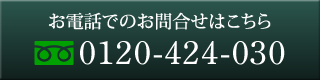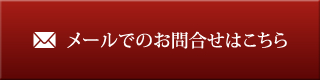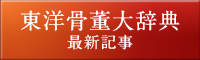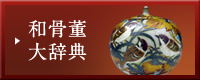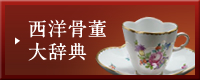8世紀中頃に書家や僧として活躍しました。幼い頃に仏門に入り、修行の合間に書を学んでいましたが、貧しかった故に芭蕉の葉や板を紙代わりに練習をしたと言われています。
奔放でおおらかな性格だったようですが、酒を好み、酔っては垣根や壁に書を書き散らしていた為、「狂僧」とも呼ばれました。
作品は、若いころから特に草書に優れ、王羲之の美しい書体を基盤としながらも、『狂草』と言われる奔放な字体を得意としたことが特徴です。そのため名士の集った当時の社交界でも名を知られていたといいます。
中国では唐時代の末頃から僧たちの中で手本とされ、日本でも江戸時代後期の歌人、良寛が好んでいました。