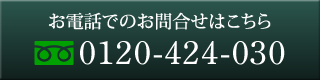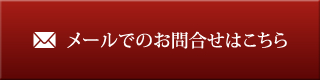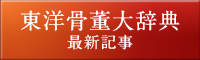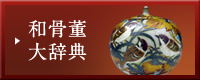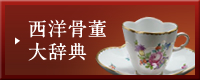17世紀に活躍した禅僧で、日本で始まった三禅宗の内のひとつ黄檗宗(おうばくしゅう)の開祖として知られています。福建省の出身で、10代の頃から仏門に興味を持っており、30代手前で出家しました。その後は師について修行を積み、40代半ばから7年間、黄檗山の主となっています。
日本には江戸時代初期、長崎にあった崇福寺に空席ができたことから招待され、約20人の弟子を率いて来日しました。その後4代将軍徳川家綱との謁見も果たし、京都に新しく寺を開創し、故郷中国で修業を積んだ寺と同じく『黄檗山萬福寺』と名付けています。こうして日本の禅界の祖となり、大正天皇から大師号を送られるなど、82歳で亡くなるまで日本で暮らしました。
書においては、墨跡(ぼくせき)と呼ばれる禅僧による書で特に才能があり、即非如一(そくひにょひつ)と木庵性瑫(もくあんしょうとう)と共に黄檗の三筆と呼ばれるまでとなっています。