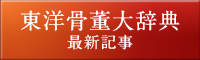青花とは、白磁に鉄や銅、コバルトなどを用いて絵付けをし、透明な釉薬をかけて高温焼成したものです。日本では『染付』、中国ではこの技法を『釉下彩』と呼び、釉薬の下に絵付けを施すため、経年による図柄の掠れや変色がないのが長所です。
中国では12世紀中頃、南宋の時代に起こった『鉄絵』という技術が元になっていると考えられており、やがて絵付けに鉄以外のものも使われるようになると、景徳鎮窯で美しい青色に発色するコバルト顔料を使った『青花』が誕生しました。その後、青花はそれより前に確立されていた鉄絵や釉裏紅よりも安定して鮮やかに発色することから、基本技法のひとつとして知られていきます。
当初、青花にはイスラム圏から伝わったコバルト顔料が用いられており、青花の制作もそのイスラム圏からの要望によって広まっていったと言われています。中東への輸出用にそれまでの中国の陶磁器製品にはほとんど見られなかった大型の皿や壺が生産され、輸出業が盛んになると、元から明の時代には青花の輸出や生産が王朝の指導下に置かれるようになりました。
このように白磁や青磁と共に、中国の輸出業の一端を担った青花ですが、その造りは年代によって少しずつ異なっています。ここでは時代ごとにその特徴をご紹介します。
☆元時代
イスラム圏からの顔料、そしてそれを用いた青花の需要という貿易経路が出来上がったことで、その技術も発展しました。この時代の大型の器によく見られるのが筆に顔料を含ませて吹きかける「吹墨」の技法で、全体に細かな斑点を吹き付けるこの技法は、中国的な模様と合わせて施されました。
☆明時代
明の時代初期には、景徳鎮窯に官窯が設置されました。この時期はコバルトの輸入が停止した時期と言われており、青花よりも釉裏紅の生産が目立ちます。しばらくして再びコバルトがもたらされると輸出用、あるいは宮廷用の青花が焼かれ、中でも景徳鎮窯は非常に美しい「甜白」といわれる白磁に青花の装飾を施し、一級品を焼き上げました。
その後もコバルトの輸入の有無によって色調は変化していきますが、淡い青味を帯びた釉薬や様々な形状の器が誕生し、はっきりとした発色のコバルトとはまた異なる上品さをもった作品が出来上がりました。
☆清時代
清時代には明時代に一度途絶えた景徳鎮窯の官窯が再開されます。宮廷から賃金を保障されたことで優秀な陶工や原料を集めることが出来た為、洗練された作品が生まれました。新たな技術よりもそれまでの技術を集結させたような作品が揃い、緻密な模様や濃淡の表現が可能となっています。
コバルト顔料も、国産のものを用いながらも鮮やかで美しい色調の表現に成功しました。