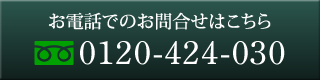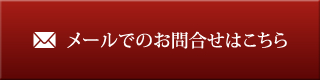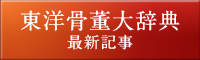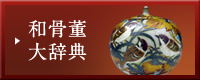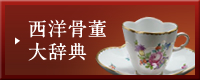中国で黒釉陶器の制作が始まったのは1世紀頃、後漢の時代だと言われています。黒釉陶器は素地に鉄を呈釉剤とした釉薬をかけ高温焼成したやきもので、浙江省北部で開発されました。
元々黒いやきものは、中国では新石器時代から焼かれていましたが、これは釉薬を使ったものではなく灰色の素地の陶器を黒色にいぶし焼きにした「黒陶」と呼ばれるものでした。徐々に技術が発達するにつれて、薄く光沢の出るまで研磨された「卵殻黒陶」が作り出され、黒釉陶器が誕生するまではこの黒陶が使われます。4世紀頃になり、黒釉陶器が盛んに焼かれるようになると、黒釉陶器の技術も磨かれていき、釉薬や彫刻、形状などについても改良が進んでいきました。
このように青磁と同じく古くから焼かれている黒釉陶器は、時代や窯ごとにいくつかの技法を用いた作陶が行われています。
ここでは窯ごとに、黒釉陶器についてご紹介していきます。
☆徳清窯
漢から唐の時代にかけて活動していた窯で、滑らかな質感の黒釉陶器を多く生産しました。「天鶏壺(てんけいこ)」と呼ばれる、注ぎ口が鶏の頭の形になっている壺や、薫炉(香炉の一種)など様々な黒釉陶器を製造しています。
☆黄堡窯
黄堡窯は耀州窯の前身として知られている窯です。耀州窯はオリーブグリーン色の青磁が有名ですが、唐の時代には黒釉陶器も製造していました。黒釉に白濁釉を掛けて焼き上げる「花釉」や、白化粧土を施した上に黒釉をかけ、模様を描いたり彫りを施すなど、黒釉陶器における多くの装飾技術を考案しました。
☆磁州窯
黒釉陶器を多く制作していました。中国最大の釜場の1つとして知られ、磁州窯系の窯場で焼かれた作品の1つに「河南天目」があります。これは素地に白化粧を施さずに黒釉を掛けたもので、磁州窯系の作品にはこれに柿色の釉薬で装飾を施したものや、黒釉の下に白泥の線を引いて装飾したものなどがよく見られます。
また、施した黒釉の一部を描き落として模様を焼成する「掻き落とし」の技法を使った作品は、磁州窯の代表作として知られています。
☆建窯・吉州窯
宋の時代、この2つの窯は黒釉陶器において特に美しい作品を生み出しました。建窯は様々な光彩を放つ「曜変天目」やいぶし銀色の斑点が特徴的な「油滴天目」、吉州窯は葉を使った装飾の「木の葉天目」などです。この2つの窯が生み出した黒釉を活かした装飾は、窯が衰退した後も人気が続きました。