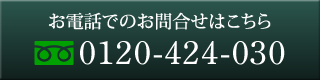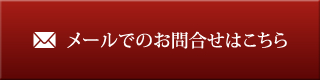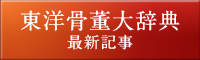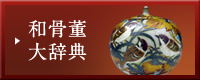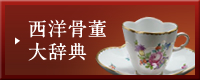8世紀中頃に書家、政治家、そして学者として活躍し応方と号しました。山東省の名門の出身で、その有能さから多くの官僚の座を歴任し、安禄山(安史)の乱で功を立てています。
しかし、気性が荒く頑固な性格であったため、政治的にも昇格と降格を体験するなど不安定でした。晩年は反乱軍の説得に派遣された際、捕らえられて殺されています。
書においては、才能のある書家を輩出する家系として知られる一族に生まれており、自身も唐時代の書道の四大家に数えられています。
顔真卿は唐の時代以降手本とされてきた、王羲之の流れるような美しい書法に反発し、特徴ともいえる端正で雄大な楷書を書きました。この技法は『顔体』といわれ、後世にも大きな影響を与えています。
特に日本では能書家として知られた真言宗の僧、空海や昭和の書家井上有一その書を好んだと言われています。