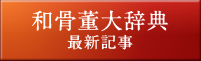20世紀初頭から半ばまで活躍した洋画家ですが、特に不透明な絵具を使用した水彩画で、素晴らしい作品を多く残しました。油彩画が主流となりつつあった当時、基本的に重ね塗りのできない水彩画で作品を描いた高い画力と、その画面の油彩画にも劣らない重厚感は彼の特徴とも言えます。
中西利雄の歴史
1900年に東京で生まれた中西は、中学から水彩画を学び始め、22歳の頃には東京美術学校の西洋画科に入学しました。在学中には日本水彩画会展に入選するなどし、5年後に同校を卒業すると28歳でフランスに渡り、約1年の間、絵画研究に没頭しています。この間に学友であり画家となった小磯良平と共に、イタリアやイギリス、オランダなどのヨーロッパを巡り、その後サロン・ドートンヌに出品した作品は入選を果たしました。
31歳の頃に日本に帰国し、帝展に出品した作品が特選を受賞すると、中西は水彩画家としてその名を広めていきます。翌年には学友たちと美術家団体「新制作協会」を発足し、唯一の水彩画会員としてその後も制作活動を続けました。
晩年は小説家大仏次郎の小説『帰郷』の挿絵を担当していましたが、病にかかったことで中断し、48歳の若さで亡くなっています。
新制作協会
1936年に発足しました。中西利雄以外に、猪熊弦一郎や脇田和、小磯良平などの9名の若い画家たちが中心となって自由さを求めて結成されています。展覧会は新制作展と呼ばれ、第一回は上野で開催されました。やがて3年後の1939年には彫刻部が、さらに1949年には建築部(のちにスペースデザイン部と改名)、1951年には日本画部が設けられ、あらゆる分野の芸術家を受け入れていきます。
現在は国立新美術館にて毎年展覧会が行われており、入選者や受賞者の数が比較的少ないことからレベルの高い展覧会であるともいわれています。
水彩画
現代では幼少期から馴染みがあり、学校などでも扱われる水彩画ですが、その起源は旧石器時代だと言われています。ヨーロッパでいうとエジプト王朝時代にはすでに写本のために使われており、以降も羊や子牛の皮などを紙代わりに水彩が使用されていました。芸術作品としてはルネサンス期(14世紀頃~)からその手法が取り上げられ、現在に至るまで、特に生物画や植物画を描く手段として用いられています。
また、日本では平安時代の大和絵や、江戸時代に流行した浮世絵の肉筆画などの手法として知られました。明治時代後半には水彩画入門書「水彩画之栞」を記した画家の大下藤次郎によって国内で大きなブームとなり、『みづゑ』(=水絵)とも称されています。