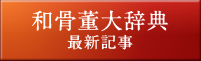『金工』とは、金属を溶かしたり、伸ばしたりという様々な加工を施し作品を制作する工芸技術です。日本では「五金」と呼ばれる金・銀・銅・鉄・錫の5種類の金属が古くから金工に使われており、これらを合わせた合金を使った技術が発展してきました。元々は人々の生活道具の1種として使われていましたが、時代が進むにつれその技術は高度に発展し、芸術作品として認識されていきます。
ここでは日本における金工の歴史を、詳しくご紹介したいと思います。
金工の歴史
金工が日本に伝わったのは紀元前3世紀頃、弥生時代のことでした。中国で高度に発達した文化が大陸との交渉によって伝来し、日本に鉄器や青銅器が伝わったのです。これに影響を受け、日本は石器を使用する文化から革新的に発達し、弥生時代には武器や祭具として銅剣や銅矛、鏡が使われ始めました。やがて石型による銅剣の鋳造や、技術が発達すると銅鐸の制作も始まり、15cmほどの小さなものから150cmを超える大型のものまで、形状や図柄など様々なものが作られていきます。
さらに、弥生時代には有名な「漢委奴国王」の文字が刻まれた金印も伝わっており、次の古墳時代には金を使った装身具や副葬品を制作する技術が広まりました。神具として重視された鏡や、指輪、腕輪、冠、耳飾り、そして馬具など、すでに当時から、鋳造技術はもちろん、彫刻や鍍金など、高い装飾技術が日本に定着していたのです。
奈良時代になると、金工技術は当時伝来した仏教美術の中で活かされるようになりました。最も有名なのは、東大寺の大仏と言えるでしょう。大小合わせた仏や菩薩、獅子の鋳造に加え、大陸から工人も渡来したことで梵鐘や鏡も大量に制作されています。中でも正倉院には多数の鏡が残っており、鏡の他にも金・銀・白銅・赤銅・錫など様々な材料と装飾技法を使った、服飾品、楽器、武器、食器などが作られました。
この時代には日本で初めての貨銭の鋳造も行われており、金工史的にも最盛期と言われています。平安時代にはそれまで中国や朝鮮文化の影響を強く受けていた装飾が純日本風になり、燈籠や鎧、兜などの工芸品も多く見られました。また、次の鎌倉時代には、武家社会の重厚な気質に沿った装飾品や武具が多く生産されています。
その後、代表的なもので言えば、室町時代には茶の湯釜、安土桃山時代にはヨーロッパ文化の影響を受けた茶道具や、城郭を装飾する豪快な金工が多く制作されるようになりました。この頃にはもう十分に日本人の間で金工の技術が広く親しまれていたことが伺えますが、江戸時代に入り鎖国状態が安定すると、社会の平穏と共に庶民の生活の向上、そして鉱山の開発などにより、金工の職人たちは需要に応えるべくさらに腕を磨いていきました。
特に江戸末期からの、刀装具や装飾品、置物などに用いられた写実性の高い装飾は人気を博し、鎖国が解禁となった明治時代には、海外で高い人気を得るようになります。
廃刀令や廃藩置県により、それまで藩や幕府の保護を受けていた腕の良い職人たちは一時職を失いましたが、明治6年に開催されたウィーン万国博覧会で日本の伝統工芸に注目が集まったことをきっかけに、政府が金工を含めた日本の工芸品の技術の高さを再度見直し、海外貿易または贈答用として、金工も高い需要を得ることとなったのです。
国内では西欧文化が流行していた明治時代ですが、水面下で金工技術も磨かれ、その技術と伝統は現代にも受け継がれています。