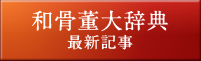愛知県瀬戸市を中心とした窯業地、あるいはその周辺で生産される陶磁器のことです。東日本で広範囲に流通したため、瀬戸焼は日本で陶磁器を「せともの」と呼ぶ由来となったやきものとされています。
中世の古窯のうち他の窯が焼きしめなどで耐水性を高めていたのに対し、実用食器に釉薬を施して焼成することで耐水性と強度を高めていたのは、猿投窯やこの瀬戸古窯が始まりと言われています。
瀬戸焼の歴史
日本でも古くから須恵器や甕器などやきものが作られてきましたが、平安や鎌倉時代になると日宋貿易によって、それまで国内で焼かれていたものよりも優れた、白磁や青磁が伝わりました。上流階級の消費者たちの間でこれら唐物の需要が高まるのに対して、庶民の間では日用雑器として「山茶碗」とよばれる釉薬を使わないやきものの生産が行われます。瀬戸窯でもこの山茶碗の製造は行われましたが、当時唯一、釉薬を使った「古瀬戸」の生産を行ったのも瀬戸窯でした。ここから室町時代までの間に焼かれた瀬戸焼は「古瀬戸」と呼ばれ、これは宋から施釉陶器の技術を学んできた加藤四郎左右衛門景正が創始とされています。
その後安土・桃山時代には茶の湯の文化も広まり、瀬戸焼は日用雑器だけでなく水差しや建水などの茶道具も製造しました。この頃から徐々に美濃焼など瀬戸焼と同じく釉薬を用いて焼成するやきものや、備前などの磁器が流通し始めましたが、江戸時代に入ると瀬戸窯は尾張藩主徳川義直によって藩から保護を受け、より発展を遂げていきます。江戸後期には瀬戸でも磁器の生産を始め、九州の有田で磁器を学んだ加藤民吉によって、丸窯という新たな窯や生産技術が伝えられました。これにより瀬戸窯は大きく発達し、良質の染付磁器の生産が可能となります。
明治期には、日本初参加となったウィーン万博に続き、フィラデルフィア万博やパリ万博に瀬戸焼を出品し高い評価を得ると、海外からの受注が増えていき、一時は生産の70%が輸出向けであったとも言われています。その後瀬戸焼は世界大戦を乗り越え、戦後にはドイツを真似たノベルティの生産が盛んになり、「セト・ノベルティ」とよばれ国内外で親しまれました。
このように平安から受け継がれてきた瀬戸焼の技法は現在でも受け継がれ、様々な釉薬や装飾技法を使った作品が生産されています。