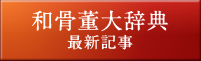愛媛県の砥部町で焼かれている陶磁器です。
焼成後の美しい白色やそこに藍色で施した呉須絵、また比較的厚みのある素地にはシンプルに表現された紋が見られることもあり、鮮やかな色絵とはまた違った味のある装飾がなされています。
砥部焼の歴史
砥部の土地では平安時代から、伊予砥(いよと)とよばれる砥石が特産品として生産されていました。しかし、この砥石を製造する際に出た砥石屑の処理には非常に手間がかかります。
そこで、この砥石屑を原料にして磁器が制作できることを知った大洲藩の加藤泰候(やすとき)が、江戸時代中期、家臣に磁器の製造を命じたのが砥部焼の始まりでした。
泰候の家臣に現場の研究開発者として選ばれたのは杉野丈助という人物でした。彼は研究を重ねましたが難航し、集まった陶工たちも徐々に減っていってしまいます。その中でも研究は続き、丈助が白い磁器の焼成に成功したのはその約2年後でした。
その後も開発は続けられ、釉薬や磁器をより白く焼成できる原料の発見がなされます。この頃にはすでに砥部焼は高い評価を得ており、多くが海外に輸出されるまでとなっていました。
さらに明治時代になると廃藩置県により、保護されていた地方の窯の技術も取り入れられるようになり、砥部焼の発展は続いていきます。アジア諸国に向けた生産やシカゴで行われた万国博覧会で賞を受賞するなど、砥部焼はその名を世界に広めていきました。
大正・明治期には不況の影響や、地方で発達した陶磁器の生産に押され、砥部焼は一時衰退します。
しかし昭和中期に民芸運動を推進していた柳宗悦が、機械ろくろなどで製造方法が近代化していく中、手造りを続けていた砥部焼を称賛し再び注目が集まったことで、砥部焼は再び技術の向上を図り、1976年には伝統工芸品として認定されました。